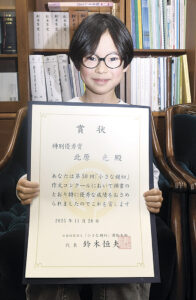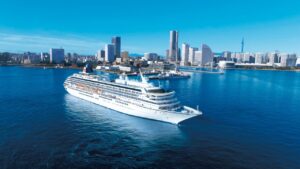国産漆確保へ整備作業 木曽漆器工業協同組合が塩尻・松本で草刈り
2025/07/20
後で読む
塩尻市の木曽漆器工業協同組合は18日、同市片丘と松本市中山に設けているウルシの育成林で草刈りなどの整備作業を行った。地元産の漆を生産しようと長年にわたって育成に取り組んでいる。組合関係者や県と市の職員ら約40人が各所に分かれて汗を流した。
片丘の小丸山農村広場近くでは100本程度の木が、根元近くの直径で20センチ前後に育っている。参加者は一帯に生えた下草を草刈り機で丁寧に刈り取った。この育成林では来年にも、漆器の材料になる漆を採る「漆掻き」を試す考えだ。
国産漆の生産が減少している一方、国が文化財には国産漆を使う施策を打ち出しているため、産業向けの流通量が相対的に少なくなっている。全国の漆器産地でウルシの植栽活動が進んでいるという。
地元でウルシを育てようという試みは江戸時代末期にまでさかのぼり、同組合も昭和50年代前半から取り組んできた。ただ、寒冷地で育ちにくいこと、獣害に悩まされたことなどからなかなか定着しなかった歴史がある。
地元での漆の確保は、価格や供給がより安定することにつながりそうだ。組合の小林広幸理事長(67)は「産地としての責務を果たし、よりプライドを持って漆器を作れるようにしたい」と話していた。