響く斧の音 古式ゆかしく 伊勢神宮の式年遷宮 上松で御杣山伐木の儀
2025/09/18
後で読む
伊勢神宮(三重県伊勢市)の社殿を20年に1度造り替える式年遷宮行事の一環として、ご神体を納める器の御用材を伐採する祭儀「御船代祭」が17日、神宮の内宮で行われた。上松町の小川入国有林では、同時刻に「御杣山伐木の儀」が営まれ、御船代に使われる木曽ヒノキの伐採が行われた。木曽の森に響いた斧の音が、古式に則った神事の重みを静かに伝えた。
器「御船代」は、ご神体を納める「御樋代」をさらに納める神聖なもの。6月には町内で御杣始祭が開かれ、御樋代用のご料木が切り出された。
斧だけで伐採する伝統技法「三ツ紐伐り」で、保存会の10人と神宮職員5人が樹齢約300年のヒノキを2時間かけて伐採。杣頭の橋本光男さん(73)=上松町=は「経験のない大木だったが、無事に倒せてよかった」と語った。
天皇陛下の「御治定」が下されれば、来春には「仮御樋代木」の伐採式が町内で営まれる見通し。橋本さんは「若い人の意見も取り入れながら次世代につなげたい」と話した。
御船代祭は19日に伊勢神宮外宮でも行われ、岐阜県内でも伐採作業が行われる。







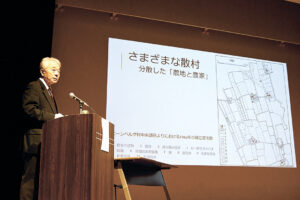



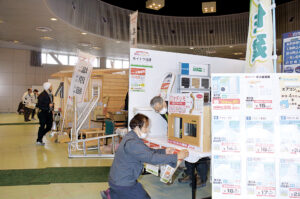


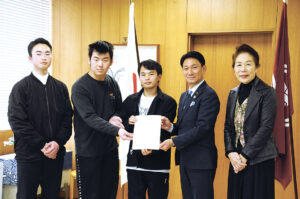




-300x200.jpg)




