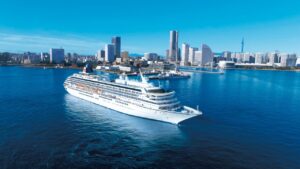松本城天守の築造は「1594~97年頃」 柱の年輪調査から判明
2025/11/07
後で読む
松本市は6日、これまで諸説あった国宝松本城天守の築造年代について、「文禄3(1594)年~慶長2(1597)年頃」とする最新の調査結果を明らかにした。柱の年輪から築造年代を算出する科学的な調査に基づき導いた。これまでの市の公式見解では「文禄2~3年頃」だった。大天守の30年ほど後に月見櫓と一緒に増築されたとする辰巳附櫓の建設時期が大天守と同じとみられることも判明した。
調査は令和4~6年度、「近世城郭の天守群」の世界遺産登録に向けた推薦書を作成するための基礎研究の一環。奈良文化財研究所名誉研究員の光谷拓実さんが天守5棟の柱の年輪を調べたところ、
大天守に使われていたヒノキの柱4本が、いずれも「1596年」(文禄5年・慶長元年)に伐採されたと分かった。
名古屋工業大学名誉教授の麓和善さんは「当時は木材を乾燥させず、伐採後すぐに1から6階まで短期間に建設されたと考えられる。土台となる石垣の築造に2年ほどかかることから年代を特定した」と述べた。
辰巳附櫓は天守から櫓に入る出入り口に壁の跡が確認されないため、大天守、乾小天守、渡櫓と同時期に建設されたとみられる。城の様式は、天守完成期の特色を持つ「層塔型」のごく初期の特徴を備え、初代松本城主の石川数正、康長親子が先進的な城づくりをしたことが伺えるという。
天守の創建年代については諸説あり、平成2(1990)年に「国宝松本城築造年代懇談会」が検討した結果を公式見解としていた。臥雲義尚市長は「科学的な根拠が示されたことは非常に重いものと受け止めている。総合的な検討の上で市の公式見解を切り替えることになるだろう」と述べた。