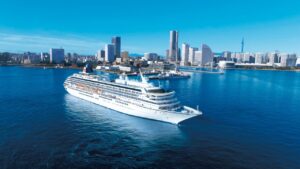塩尻・床尾中央遺跡で70軒の住居跡発見 貴重な遺物も続々と出土
2025/10/31
後で読む

塩尻市教育委員会が本年度発掘調査を進めてきた、宗賀の床尾中央遺跡から70軒の住居跡が見つかった。縄文中期(5100~4800年前)、古墳時代(4世紀頃)、平安時代(11世紀頃)の三つの時代にわたって集落が形成されており、土偶など遺物の出土も数多く「想像以上」(市教委)の結果だという。

住居跡は縄文中期が39軒、古墳時代と平安時代で31軒に上る。規模が大きいと古墳時代で1軒が50平方メートルある。一つの集落は5~10軒とされ、発掘現場では、時期を変えて何軒もの住居跡が重なるように作られた様子が分かる。かつては近くに川があった環境も踏まえ、平出博物館の小松学館長は「住み続けるには魅力的な場所だったのでは」と推測する。
出土品は釣手土器だけでも6、7点見つかった。塩尻市で2例目、松本平でも3例目となるという、縄文時代の三角柱状の「三角とう形土製品」は大きさは幅7.1センチ、厚み4センチ、高さ6センチで、穴が開く。祭祀の道具とみられている。
調査は、住宅団地の造成に伴い5月に始まった。対象面積は約4700平方メートル。10月30日が作業員20~30人を動員する発掘最終日で、信州大学情報・DX推進機構の単麟准教授による現場の3Dデータ(立体、空間情報)の記録作業も行われた。調査結果は来年2月に平出博物館で速報展として紹介、来年度に整理調査をし報告書を作成する。小松館長は「これだけ面的な発掘ができる機会はなかなかない。三つの時代のピークが分かる。すごい遺跡があると知ってほしい」と話す。