ナチス時代の礼状、松本に ドイツ・歓喜力行団が送る
ナチスドイツ時代の1930年代に、ナチ党の労働団体・ドイツ労働戦線の下部組織として設立された歓喜力行団(かんきりっこうだん)から、松本市本町の商家に送られた礼状が、松本市寿台7の水琴堂書店に保管されている。当時、本町に店を構えていた水琴堂の先々々代・小松為吉(故人)宛てとみられるが、90年前のいきさつを知る手掛かりはなく、詳細は分かっていない。地域の埋もれた歴史を示す記録として希少性を指摘する声がある。

歓喜力行団は、労働者をナチ体制に統合する目的で設立されたドイツ労働戦線の一部局として1933年に発足した。「喜びを通じて力を」を意味する名称にあるように、富裕層の象徴だった娯楽や旅行を労働者に提供。恩恵を通じて労働者を管理・統制し、政治体制を安定化させるとともに、労働力を強化し、国家目的への動員を図る狙いがあったという。
礼状は歓喜力行団ハンブルク支部第4支局長・ブロートマイヤー名で出され、日付は「193□年2月23日」となっている。西暦の下1桁が欠落しているが、ドイツ現代史が専門の田野大輔・甲南大学教授は、1936年に歓喜力行団が開催した世界厚生会議を機に、日独間の社会政策面の交流が進んだ1936~38年の間のやり取りとみる。書面にはドイツ労働戦線の透かしが入り、ハンブルクの囲碁愛好家に鮮やかな木彫りの人形を贈ったことに対する謝意が記されていた。
水琴堂の小松将彦社長(44)によると、同店は明治時代に創業し、本町に店を構えた当時は筆墨紙や書物類のほか、西洋小間物を取り扱うなどした。1930年代の松本では旧制松本高校にドイツ人教師が在籍するなどしたが、ドイツとの民間交流の経緯は分かっていない。店が現在地に移転した後も、代々伝わる古文書などと共に礼状を保管してきたという。
田野教授は「日本の代表団や政府関係者がナチ党と交流した類いの記録はドイツに多数残されているが、今回のような民間交流はあまり聞いたことがない」と話す。個人的な交流だった可能性に言及しつつ「仮にドイツと松本市との交流の実態が分かればそれなりの資料価値が出てくる」と指摘する。
松本市文書館は「埋もれていた歴史の一端が垣間見えて興味深い。さまざまな記録を通して当時の郷土が解像度を増してくる」と関心を示している。



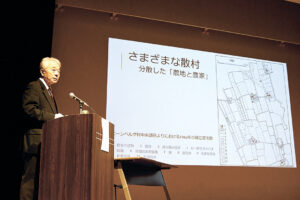



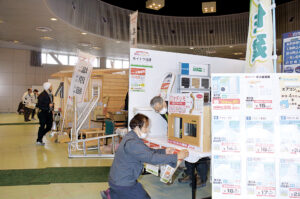





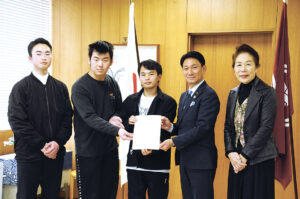




-300x200.jpg)




