松本にも響いた空襲警報 戦争末期に高まる緊張

いよいよ松本も空襲になる。そんな不安と緊張が広がっていた―。松本市中央2の横沢徳人さん(91)は、太平洋戦争末期の昭和20(1945)年をそう振り返る。
松本城下の老舗・知新堂の4代目。太平洋戦争中は開智国民学校の児童だった。当時の家業は紙・印刷業だったが、戦中は従業員も皆出征し、本町の店舗はラジオ修理の相談所として貸し出されていた。
初めて米爆撃機B29を目にしたのは20年5月。市内の城山での開墾作業中、巨大な機体が上空に姿を現し、教員の号令でとっさに体を伏せた。同日、安曇野では有明空襲が発生。横沢さんたちも機銃掃射などに備え、慌てて帰宅したという。
7月に入り、山梨県が甲府空襲に見舞われると、次は松本だという緊張が高まっていく。松本上空に飛来した米軍機から空襲予告ビラがまかれ、縄手入り口の火の見櫓の半鐘や空襲警報が鳴り響く日が増えた。「子ども心に恐ろしかった」
そもそも松本は軍都として発展した側面を持つ。歩兵五十連隊が置かれ、郊外には陸軍飛行場があり、軍需工場の疎開が進められていた。横沢さんは四柱神社で武運長久を祈願し、隊列を成して出征していった連隊兵士たちの軍歌を今も覚えている。女鳥羽川沿いの萬屋旅館には特攻隊が駐留し、出撃前は宿の上空を旋回して九州へと飛び立っていった。「戦争が長引けば、本当に松本も攻撃を受けていたかもしれない」
20年8月、広島と長崎の街を新型爆弾が全滅させたという報が松本にも届く。このころ横沢さん一家は里山辺の親戚宅に疎開していた。そして迎えた15日。疎開先から本町の自宅に荷物を取りに帰り、中町通りのマルタン電気店で終戦を告げるラジオ放送を聞いた。「玉砕してでも戦えと、本土決戦を告げる内容を想像していただけに判断がつかなかった」。里山辺に戻る道すがら人影はなく、どこもかしこも静まりかえっていた。
戦後も食糧難や物資の不足は何年も続いた。「本当に大変な時代だった。戦中も戦後も必死だった」。身近にあふれていた多くの戦災孤児を思い出すと、今でも涙がこぼれる。




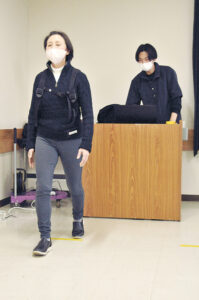





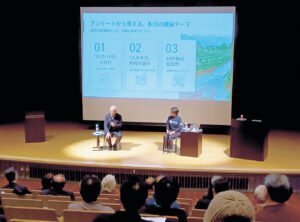

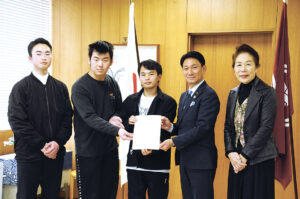




-300x200.jpg)




