大正5年「白板橋」の親柱 松本市今井の村山さん宅に残る 歴史知る重要な資料

松本市今井の農家・村山誠仁さん(87)の自宅庭に「白板橋」と書かれた親柱(橋の名前や竣工年が記されている柱)が残されている。松本駅西の国道143号巾上交差点北側で女鳥羽川に架かる「白板橋」の昔の親柱とみられ、対になるもう一つの柱には「大正五年八月竣工」の文字がみえる。白板橋では現在、掛け替え工事が進んでおり歴史を物語る貴重な資料ではと注目を集めている。
親柱は、地元・北耕地公民館の建設のために、村山さんが高校を卒業して間もない昭和30(1955)~33年ころ、現在のテレビ信州松本支社(丸の内)の場所にあった丸の内病院の工事現場からもらってきたもの。当時は大きな石は貴重で、地元の仲間と大勢で赴いた。いろいろもらった中で親柱は公民館建設に使わず、歴史が好きだった村山さんの父・文人さん(故人)が譲り受け牛車に乗せて自宅に持ち帰った。
市文書館特別専門員の窪田雅之さん(69)は、白板橋は明治11(1878)年の建設時は木製だったが、その後何度か建て替えられ「大正5(1916)年以前に石になっていた可能性がある」とする。同じ女鳥羽川に架かる千歳橋は明治9年に石製になっている。窪田さんは廃仏毀釈で廃寺になった寺の石材の転用が頻繁だったことに触れ「古い白板橋の石材が病院建設に使われ、その後に北耕地の公民館建設に転用されたとしても不思議はない」とする。
巾上町区町会が平成12(2000)年に発行した「庄内村幅上 巾上町区町史」には、昭和34年8月の台風7号による女鳥羽川の氾濫を教訓として、道路拡幅に伴う白板橋のかさ上げに備えて、37年3月に橋脚のない「プレート・ガーター橋」が竣工したことが記されている。窪田さんは「見つかった親柱は白板橋の歴史を知る上で貴重な資料。大切に保管してほしい」と話している。







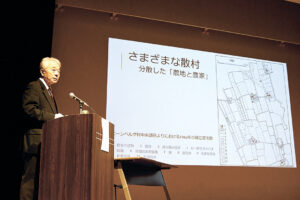



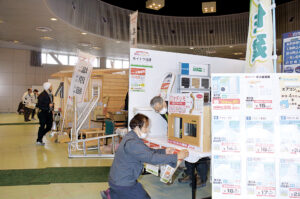


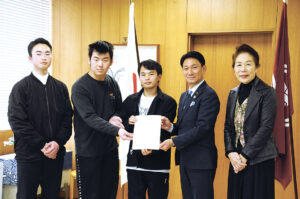




-300x200.jpg)




