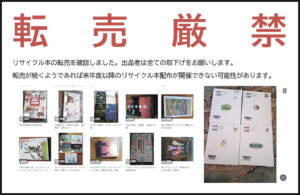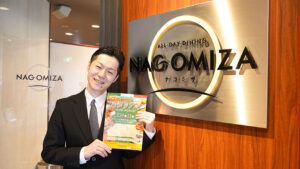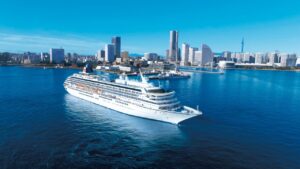「戦争は修羅道」生き方を問う 松本の洞光寺に僧侶が描いた「地獄変相図・心業十趣図」
2025/09/26
後で読む
松本市刈谷原町(四賀地区)の洞光寺に、戦後間もない昭和29(1954)年に描かれた「地獄変相図・心業十趣図」がある。人々に勧善懲悪を教え諭す絵として、第16世・俊善和尚(昭和32年没)が手掛けた扁額で、仏教において衆生が転生する六つの世界(六道)を分かりやすく描写している。一風変わっているのは六道の一つ「修羅道(阿修羅道)」に戦争を描いている点で、戦後80年がたつ今も、参拝者らに「いかに生きるか」を問い続けている。
「地獄変相図」と「心業十趣図」が対になったヒノキ板の扁額で、いずれも縦約90センチ、横約1.8メートル。六道の最下層に当たる地獄道にはじまり、飢えと渇きの餓鬼道、弱肉強食の畜生道など、生きとし生けるものが生前の行いに応じて生まれ変わる世界を俊善和尚が自ら描いた。
修羅道は一般的に鬼神・阿修羅が住む争いの絶えない世界とされるが、描写されるのは爆撃によって吹き飛ぶ兵士ら人間同士の戦争の姿だ。「にくしみ/争い/戦い」の言葉が添えられる。第19代の松本諦宗住職(47)は「戦争の時代を生きた俊善和尚にとって、修羅とはまさに戦争そのものだったのではないか」と話し、戦没者を弔ったであろう俊善和尚の胸中を推し量った。
2枚の扁額は悪行を思いとどまるための教えであるとともに、罪や過ちは心から悔い改めることで、仏の慈悲が差し伸べられることを示すものでもあるという。並んで本堂に掲げられており、今夏は市立博物館の特別展「地獄の入り口」にも出展されて注目を集めた。松本住職は「一介の僧侶が描いた絵から、より良く生きようとする姿勢こそが尊く大切なものであると教えられる。今日にも通ずるものだろう」と話している。