日本最高所の池・御嶽山の二ノ池 噴火の火山灰流れ込み消失
2025/08/26
後で読む
御嶽山(長野・岐阜県境)の山頂直下に位置し、日本最高所の池として知られていた「二ノ池」が、令和6年をもって完全に消失した。平成26(2014)年の御嶽山噴火で積もった大量の火山灰が雨や雪解け水によって流れ込み、標高2905メートル(国土地理院のデータでは2913メートル)にあってコバルトブルーの水をたたえていた池の様相を一変させた。御嶽山科学研究所(木曽町開田高原)代表の國友孝洋さん(理学博士)が24日、町内で開かれた講座で見解を示した。

26年の噴火直後、二ノ池はすぐには消失せず、形状を保っていた。これは火砕流が二ノ池を避けるように流れたためで、池には上空から降った火山灰が約4センチ積もったのみだった。一方、二ノ池への「集水域」となっている火口周辺には50センチ以上の火山灰が堆積した。28年から二ノ池は徐々に縮小し始め、特に30年から翌年にかけて急激に縮小した。國友さんはその原因として、30年の多雨と令和元年5月に発生した雪崩および泥流を挙げている。
國友さんによると、二ノ池は少なくとも千年ほど前から存在していたとみられる。「26年の噴火は、水をためる器(くぼ地)そのものを、わずか10年で埋めてしまった。それほどの出来事だった」と語る。有史以来の噴火だった昭和54(1979)年には火口周辺に多量の降灰はなく、平成3(1991)年と19年の噴火は規模が小さく、池への影響はなかったという。
現在、二ノ池は砂地のような状態で、雨天時に一時的に水が流れる程度。池の復活について國友さんは「周囲に土砂が堆積して再び水がたまる環境ができるか、川が曲がる箇所が深く掘れて渓谷の縁のような形で池ができるか、あるいは新たな水蒸気噴火によって水がたまる穴が形成されるしかない」との見解を示した。

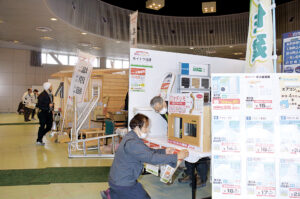








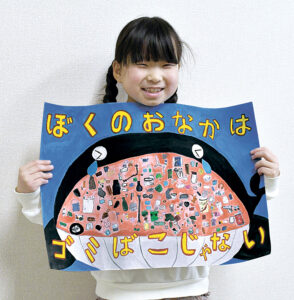


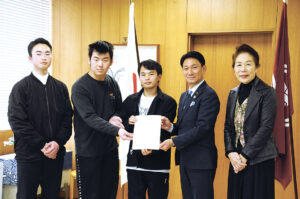




-300x200.jpg)




