暮らしも学校も戦時一色 福島昭子さんが振り返る
戦時中の記憶は、戦後とは比べものにならないほど、鮮明なのだという。食料増産、親族の出征、戦死、敗戦…。「大変な時代にいるということを子供心に感じていたのだろう」。松本市蟻ケ崎1の福島昭子さん(92)は80年前をそう振り返る。
昭和7(1932)年、麻績村に生まれた。太平洋戦争の開戦は国民学校3年生の時。「学校とは名ばかりで勉強はほとんどやらなくなった」。山野では足りず校庭も開墾し、日々供出用の農作物を育てた。米、麦、カボチャ、サツマイモ…。戦況の悪化に伴い、労働は増えていったという。燃料用の松根油を採りに行ったり、武運長久を願って出征兵士に手渡す千人針を縫ったりすることも。いずれも授業の時間が充てられた。
強烈に覚えている出来事がある。隣に暮らす親戚の“兄さん”の出征だ。10歳余り年上で県庁勤め。家族のような付き合いがあり、福島さんをかわいがってくれた。親戚宅で開かれた壮行会には親族や隣近所が大勢集まり、軍歌が勇ましく響いた。出立の時、福島さんが思わず兄さんの足にしがみつき、顔を見上げると「行ってくるね」。優しくなでてくれたように記憶している。しかしそれきり、兄さんは戻らなかった。
「天皇陛下万歳なんてうそですよ。家族を思って死んでいったはず。南方のどこかに眠る兄さんを思うと今でも涙が出ます」
昭和20年8月15日は昼に天皇陛下の放送があると聞き、外仕事を早くに切り上げた。自宅庭に家族や近隣住民が集まり、ボリュームを上げたラジオに聞き入った。日本は負けたんだ─。20人ほどが居合わせたが皆静まりかえっていたという。「これで自分たちも馬場の池(聖湖)に身を投げて死ぬんだ」。とっさにそう思った。「お国に殉じろと教育されていましたから」。死に対する恐怖はなかったが、幼い弟妹を思うとつらかった。
戦後は新憲法の下、人権や男女共同参画に意識を傾け、町会役員や市議会議員を歴任。社会教育や平和教育にも力を注いだ。子供を産み育てる中で、命をあやめる戦争の罪深さを一層痛感したとも話す。「丸い地球に暮らす人間同士が争うなんてあってはいけない。戦争で命を落とすのは私であり、あなたなのだから」





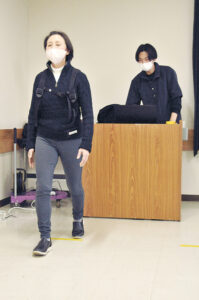





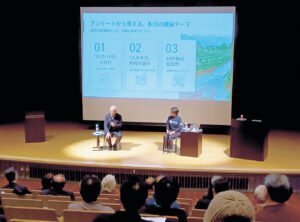

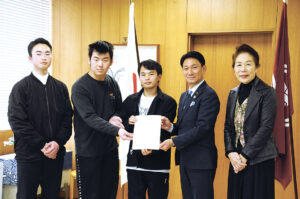




-300x200.jpg)




