安曇野市内で外来植物ナガミヒナゲシの分布広がる 素手で触れるとかぶれる恐れ
安曇野市は、市内で分布が広がっているケシ科の外来植物・ナガミヒナゲシの注意喚起を始めた。この時季に道路脇や田畑のあぜなどで淡いオレンジ色の花を咲かせており、場所によっては群生している。茎や葉にアルカロイド性の有毒物質が含まれるため、皮膚が弱い人はかぶれやただれの心配があり、市は素手で触らないように呼び掛けている。
国立環境研究所の侵入生物データベースなどによると、欧州地中海沿岸原産で花は直径3~6センチ。昭和35(1960)年に初めて東京で確認された。繁殖力が強く、1株にできる種子は最大で16万粒と言われる。根から出る物質が他の植物の生育を阻害する「アレロパシー活性」が強いのも特徴だという。
市は、「特定外来生物リポーター」に登録している住民から「ナガミヒナゲシが最近増えている。毒性もあるので、子供が触れないように注意喚起してはどうか」と情報提供を受け、初めて注意喚起することにした。
県環境保全研究所によると、標本の記録が残る中では、北佐久郡軽井沢町で昭和59(1984)年に採取された個体が県内で最初と考えられる。中信地域では、平成5(1993)年に松本市で採取された標本が同研究所に収蔵されている。遅くとも80年代には県内に入ってきていた可能性があるという。
10年以上前から自宅の庭先にちょこちょこと出始めたという農家の女性(65)=安曇野市穂高=は「よその敷地に生えると迷惑をかけるので、むしるようにしているが、根絶やしにはならない。増やさないようにはしている」と語った。
環境省が駆除の対象としている「特定外来生物」には指定されていないが、生態系に大きな影響を与える外来植物として駆除を求める自治体もある。
安曇野市は市民に駆除までは呼び掛けていない。環境課は「駆除するような段階の植物ではない。特定外来生物と比較し、放っておいても相対的に影響は大きくない。緊急性や危険性は高くないだろう」としている。




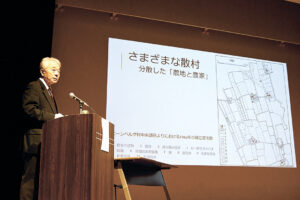



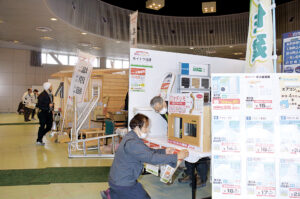





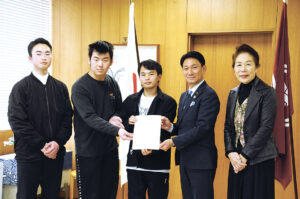




-300x200.jpg)




