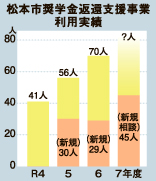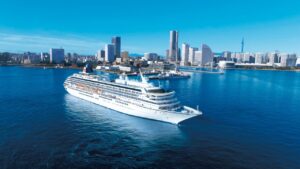4車線化が広丘地区の発展促す まつもと道路交通考・第5部② 19号拡幅、塩尻市が先行
塩尻市内の国道19号「塩尻北拡幅(2.8キロ)」と「塩尻拡幅(3.3キロ)」の両事業は、いずれも昭和55(1980)年度に都市計画決定した。松本市境からJR広丘駅周辺までの塩尻北は同58年度に事業化され、平成24(2012)年度に全線が4車線となった。事業化から30年近くを要した。事業費は約200億円。塩尻拡幅事業は現在、調査設計・用地買収などが行われている。
塩尻市内ではなぜ、松本市境の広丘吉田から道路拡幅事業が始められたのか―。長野国道事務所によると、当時建設中だった長野自動車道塩尻北インターチェンジ(IC、広丘吉田)の開通(昭和63年3月)を控え、高速道路への進入路付近の道路整備に合わせて事業化された。
塩尻北拡幅区間では複数の土地区画整理事業が行われ、宅地利用が進んだ。車の混雑時平均旅行速度(平均の走行速度)は昭和58年の29.7キロから、4車線化後の平成27年に36.7キロと約2割向上した。塩尻北ICへのアクセス性向上を捉え、市は複数の工場団地を整備して企業を誘致したほか、市内に事業所のある製造大手のセイコーエプソンが規模を拡大するなどで平成27年の製造品出荷額が県内1位(昭和55年は県内7位)となるなど社会経済情勢に大きな変化をもたらした。
JR広丘駅は平成19年に今の橋上駅舎の利用が始まった。市は駅舎の建て替えに併せ東西自由通路や東口交通広場などを整備、西口のみだった改札口が東口(国道19号側)にもでき利用者の利便性が向上した。
塩尻市吉田地区に住む50代の女性は「歩道が広くなり自転車で通行しやすくなった。開通前は車道が迫っていたので歩道を通るのも怖かった」と話し「沿線に新しい店舗が次々にできている」と好意的に捉えている。一方で「渋滞ポイントが解消したわけではない」ともいう。国道から東西へ一本入った市道などの生活道路が抜け道として利用されることも増えたといい、子どもや高齢者の安全対策も必要だと指摘した。