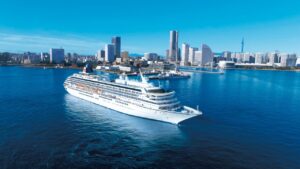2025.8.4 みすず野
2025/08/04
後で読む
歳時記に「涼し」は夏の季語と教わる。意外だったため解説を見ると、夏の暑さのなかにあってこそ感じられる涼気をいう、と載っていた。別の解説書には「涼しさを求める人々の気持ちが、夏の季語として定着させた」とあった◆信州ゆかりの俳人・小林一茶は50歳すぎに「大の字に寝て涼しさよ淋しさよ」を得た。継母や異母弟と長く争った遺産問題が解決して、故郷に定住した後の作品という。漂泊を経て家を構えた一茶が、大の字に寝て心地よい涼しさを満喫している。安堵や満足感を得ている一方、それを分かち合う人のいない独り身の寂しさが同居する◆夏を涼しくしてくれるのに昔からあるのが怪談話。古くからあり今なお有名なのは「東海道四谷怪談」だろう。文政8(1825)年に江戸の中村座で初めて上演されたという。ちょうちんから飛び出すお岩、お岩と小平の遺体が瞬時に入れ替わる演出といった、大がかりな仕掛けが観客を驚かせたそうだ。児童書に載っていた◆電気が使われていなかった時代の人は涼を取るため工夫を凝らした。すだれやよしずを使ったり、打ち水をしたり…。工夫する気持ちを倣いたい。